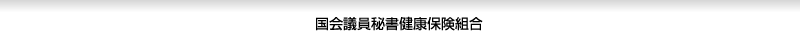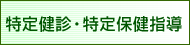  |
| トップページ ≫ ■健康保険の給付・・・「赤ちゃんが生まれたとき」 |
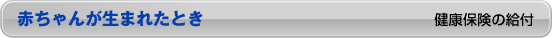
被保険者・家族(被扶養者)が出産したときは、出産育児一時金(A)と出産育児一時金付加金(B)が支給されます。
また、赤ちゃんを被扶養者にする場合は、手続きが必要です。 |

| 出産育児一時金の受け取り方には、「直接支払制度」と「受取代理制度」があります。どちらの制度に対応しているかは医療機関等の規模などによって異なりますが、どちらも国会議員秘書健保から医療機関等に直接支払われ、窓口での支払いは出産費用との差額だけで済みます。 |
| また、上記の制度を利用せず、出産後に窓口で出産費用の全額を支払い、あとで当健保へ支給の申請をする方法もあります。詳しくは国会議員秘書健保へお問い合わせください。 |
 |
「直接支払制度」か「受取代理制度」を選ぶ
医療機関等によって、どちらの制度に対応するか異なりますので、各医療機関等にお問い合わせください。 |
 |
出産育児一時金(A)を請求する
事業主(議員課担当窓口)に出産育児一時金等の申請書を提出します。
「直接支払制度」の場合・・・「出産育児一時金等内払金支払依頼書」
「受取代理制度」の場合・・・「出産育児一時金等支給申請書(受取代理用)」
出産育児一時金(A)の額※より、出産にかかった費用が少ない場合は、その差額が支給されます。
※50万円(産科医療補償制度未加入の医療機関は、48.8万円) |
 |
出産育児一時金付加金(B)を受けとる
被保険者名義の口座に振り込まれます。
国会議員秘書健保の付加金は98,000円です。 |
|
 すみやかに すみやかに |
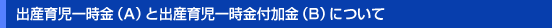
| 出産育児一時金(A)は、妊娠4ヵ月(85日)以降の出産であれば、早産、死産などを問わず支給の対象となり、双子の場合は2人分が支給されます。なお、妊娠22週以降の出産に限り(死産などを含む)、産科医療補償制度の費用を加算した額が支給されます。 |
| 退職(資格喪失)後についても給付が受けられる場合があります。 |
| 出産育児一時金付加金(B)とは、国会議員秘書健保独自の給付です。退職(資格喪失)後はこの給付を受けられません。 |

| 事業主(議員課担当窓口)に「健康保険被扶養者(異動)届」と認定のための必要書類を提出します。 |
 |
赤ちゃんを被扶養者にする
事業主(議員課担当窓口)に「健康保険被扶養者(異動)届」と認定のための必要書類を提出します。 |
 |
新しい保険証を受けとる
事業主(議員課担当窓口)から「保険証」を受けとります。 |
|
 5日以内 5日以内 |
|